日本人は『お金の教育』を受けて育っていません。その為、正しいお金の知識や長期的に資産を形成する方法、お金の扱い方などを知りません。「国に頼らずに生きて行ける人生設計」のためには『お金の教育』は欠かせないと考えています。 現在の情報社会では、インターネットで何でも調べることは出来ますが、数がとても多く、どれが正しいかを判断するには多くの時間と労力を必要とします。何を選ぶのか、何が正しい答えなのかをこの資産設計塾を通して学んでください。


資産設計塾では、お金のプロフェッショナルである当塾長が動画を監修しています。基本的な経済・金融の知識から投資・会計・ITリテラシー・不動産・社会保険など、1コンテンツ5分~15分程度の動画に編集・開発したオリジナルコンテンツは、分かりやすさ、面白さが、魅力です。

資産設計塾を学ぶにはスマートフォンさえあれば学ぶことができます!現在、通信環境も急速に整えられ、安定して、いつでも、どこでも、何度でも好きな時間で学ぶことが可能です。

贈与や遺贈・相続に関する基礎知識から、個人に関わる税金の基礎知識など、税理士有資格者が監修した動画コンテンツで分かりやすく学ぶことが出来ます。 また、当塾長はファイナンシャルプランナーで、DC(企業年金)プランナーで、宅地建物取引士でもあります。さらに、不動産投資家としても数十億規模の投資を実践してきています。机上の知識ではなく経験に基づいた動画はとても興味深く見られることでしょう。
※税理士有資格者とは、税理士試験5科目合格者(試験科目免除者を含む)のうち、税理士会に登録していない未登録の税理士資格有資格者をいう
お金についての学び直しに、遅いということはありません。 一から資産形成をしたい場合にも、まとまった資産を運用をしたい場合にも役立ち、金融について学んだことがキャリアアップの一助となることもあります。 特に、人生のさまざまな分岐点がある30代40代においては、一度立ち止まって経済について学び、 理解を深めることで今後の人生設計をしっかりと考えられるようになるでしょう。
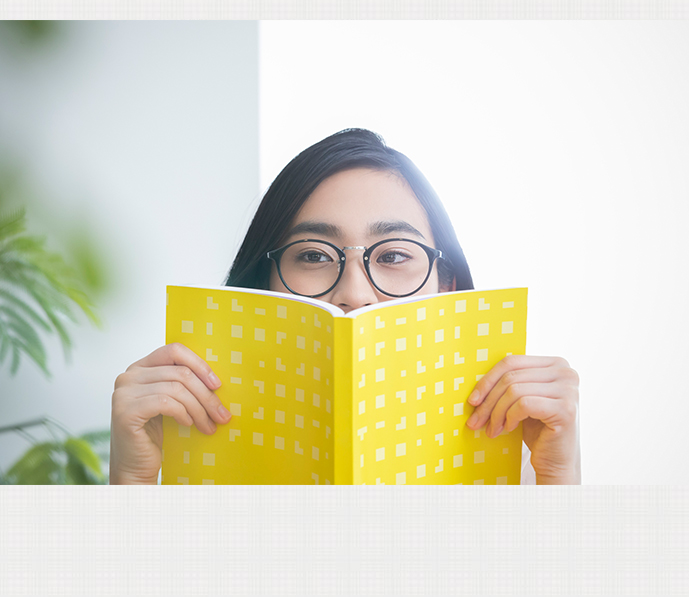
資産設計塾では、資産設計三分野を理解し実践することで
豊かな人生を送る人を創る目的でカリキュラムの構成をしています
資産設計三分野とは
【資産形成】ゼロから資産をつくる
【資産運用】出来た資産を殖やす・活用する
【資産承継】殖えた資産を次の代に受け継ぐ
これらの詳細について
全12章に分けて160を超える動画で解説

経済用語・経済事象や金融用語・金融商品などの基礎を学び、次の分野以降の理解に役立てる
0.第1章の目的
1.経済とは
2.GDPとは
3.金融とは
4.為替レートについて
5.ドル円レートの歴史
6.為替レートと輸出・輸入
8.デノミとは
9.金利・利率・利息・利子・利回り
10.銀行の役割
11.日本銀行の役割
12.株式と株主のメリットとリスク
13.株式上場IPOについて
15.債券について
16.ファンド(投資信託)とは
17.保険とは

健康保険制度、年金制度などの社会保険制度を学び、その手厚さが我が国の国家財政に如何に負担を与えているかを学ぶ
0.第2章の目的
2.公的な社会保障概要2
3.公的な社会保障概要3
4.公的年金1
5.公的年金2
6.公的年金3
7.手厚い社会保障の弊害1 高い社会保険料
8.手厚い社会保障の弊害2 上がる消費税率
9.手厚い社会保障の弊害3 年金制度の崩壊
10.手厚い社会保障の弊害4 国家財政の危機
11.国にお金を貸しているのは
12.個人資産と国の借金の関係
13.国家財政を立て直すには
14.金融緩和によるインフレ誘導
15.金融緩和の真の目的に迫る
16.国家と国民の関係
17.国家破産と回避策

日本の義務教育では決して触れられることのないお金に関しての真相を理解することができる
0.第3章の目的
1.お金の役割
3.合成の誤謬とは
4.発想の転換
5.お金の価値は一定ではない
6.絶対価値について
8.借金で何が買えるのか
9.ローンとクレジットの違い
10.カードには3種類がある
11.クレジットカードの基本
12.カード手数料は誰の負担か
13.カードの得する使い方
14.カードの損する使い方
15.世の中に無料のものはない

ITは誰のためにあるものなのか?どのようなリテラシーが今後は必要になるのか?を理解し、スマートフォンの基本操作をマスターすることができる
3.嘘の情報に惑わされない
4.コンピューターの基礎を理解する
5.文字コードとは
6.画像形式の違いと特徴
7.アプリケーションとOSの違い
8.インターネットの仕組み
9.ブラウザーとキャッシュ
10.スマートフォンの活用術
11.スマートフォンの使い方ガイド
12.スマートフォン決済
13.SNSコミュニケーション
14.web会議システム
15.オンラインストレージの活用
16.スマホのセキュリティ対策の必要性
17.掲載する行為に伴う責任

3つの分野の保険の基礎を理解し、自身と家族に必要な保険と不必要な保険に分けられるようになる
0.第5章の目的
1.保険の原理
2.保険の仕組み
4.保険の基礎用語
5.保険の分類
6.保険は掛け捨てが基本
8.昔と今の貯蓄性保険の比較
9.損害保険の主な商品
10.損害保険の基本
11.第三分野の保険
12.保険を適正に見直す
13.ライフイベント別保険設計

投資におけるリターンとリスク、投資と投機の違いなどの幅広い投資の知識を学ぶ
0.第6章の目的
1.貯蓄から投資へ
4.預貯金の種類とリスク
5.事業投資と金融投資のリスク
6.投機はマイナスサムゲームとなる
7.レバレッジについて
8.株式信用取引
9.アクティブファンド、ファンドオブファンズ
10.オルタナティブ投資について
11.ヘッジファンドの運用技法
12.投資と資本主義の原理

簿記の基本を学び、財務諸表三表を読めることを目指す。また、複式簿記の考えを理解し、資本主義の仕組みを学ぶ
0.第7章の目的
1.会計の基本と複式簿記の精神
2.株式会社と会計
4.勘定科目と分類
5.簿記の流れ
6.貸借対照表と資産について
7.資産の分類と負債及び資本(純資産)
8.貸借対照表の変化と分析
10.利益とは何か?
11.損益計算の基本
12.発生主義会計の概要
13.費用収益対応の原則
14.事業用資産の費用化
15.資産分類と損益計算書
16.資本循環と制度会計

所得に掛かる税金、所有に掛かる税金、消費に掛かる税金について区別して理解できる
0.第8章の目的
1.税金の様々な分類方法
2.所得税のしくみ
5.総合課税と分離課税及び損益通算
6.10種類の所得の詳細
7.所得控除と税額控除
8.所得税の申告と納付
9.所有に係る税金と消費に係る税金
10.生命保険と税金
11.損害保険と税金
12.個人が出来る節税

不動産の所有と賃貸に関する基礎知識、不動産に係る税金の知識、マイホームや不動産投資に関することが学べる
0.第9章の目的
1.不動産と登記
2.不動産の売買取引
4.不動産屋について
5.不動産に関する法規制Ⅰ
6.不動産に関する法規制Ⅱ
8.不動産に係る税金Ⅱ
9.収益不動産投資の魅力
10.不動産投資のリスク

公的年金、企業年金、個人年金から積立による資産形成方法の基本がマスターできる
0.第10章の目的
1.年金制度の全体像
2.確定拠出年金
4.積立の有効性と運用利回り
5.積立資金の確保
6.長期積立投資で資産形成
8.ドルコスト平均法による積立投資
9.長期積立投資の実際
10.純金積み立てで資産形成
11.長期積立投資まとめ
12.トンチンタイプ年金
13.NISAの基礎知識

様々な運用商品と運用法から仮想通貨(暗号資産)まで理解でき、投資詐欺に遭わない知識が身に付く
0.第11章の目的
1.資産とその分類
3.株式投資の実際
4.債券投資の実際
6.外貨建て商品の実際
7.契約者保護制度
8.金利とインフレ率
9.ビットコインについて
10.仮想通貨の分類
11.元本に関する注意点
12.投資詐欺について

民法と相続税法の基礎知識が得られる。超高齢化社会に向けて、多くの人に役立つ知識となる
0.第12章の目的
1.相続・遺贈・贈与と税金
2.民法による相続分
4.相続税計算の基礎項目
6.相続税の申告・納付
7.贈与税計算の基礎項目
8.贈与税の計算・納付、特記事項
9.相続時精算課税制度
10.財産の評価Ⅰ(不動産以外)
11.財産の評価Ⅱ(不動産)
12.相続税対策の考え方
入塾金と初年度利用料をカード決済後、すぐに資産設計塾をご利用できます。動画コンテンツをその日からお楽しみください。
初年度利用期間は、入塾日の属する月の月末までとなります。次年度以降は、年間利用料のみで継続して資産設計塾をご利用いただけます。
例)4月中に入塾された方は翌年4月末日までサイトの利用が可能です
webサイトよりお申込みを受け付けております。入塾をご希望の方はこちらのフォームよりお申込みください。⇒ 入塾お申込みフォーム